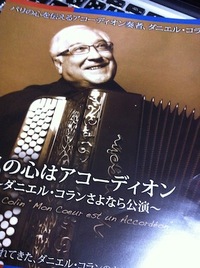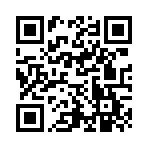2009年12月24日
第九と明日に架ける橋。
久々にブラームスの交響曲第一番が聴きたくなり作業のBGMにかけてみました。
聴いてるうちにベートーベンの第九を思い出しました。ブラームスの一番はベートーベンの第九に匹敵する交響曲をというような感じで作られたと言われてますが、メロディーが似てるところがあります。個人的には重厚で好きです。もしかして、テレビでのだめの再放送をやっていてどこかで刷り込まれたかもしれません。
私の中では年末だから第九、でも第九は聴き飽きたので似たやつ、でブラームスだったようです。もしかして、テレビでのだめの再放送をやっていてどこかで刷り込まれたかもしれません。
岡山にいた高校生の時、市民合唱に参加して一度だけ第九を歌ったことがあります。ドップラーフーガのとこの「ザーィントゥムシュルンゲン」って切り込んでくるテナーのパートが歌いたくてテナーで応募したのですが、声域が合わずベース行きを命じられました。全体練習でお目にかかった、近藤先生という合唱指揮者の先生がむっちゃ怖くてびびりました。合唱ってとてもストイック。合唱部とか無理だと思いました。でも、いざゲネプロの時に指揮者のコバケンさんが来て指揮したときに、合唱の練習でやったとおりにふったのでもっとビビりました。そういえば練習の時に、近藤先生が「ボクが指揮者と同じように振るから本人が来たら同じように歌ったらいいから」とか何とか言ってたのを思い出し、なんか音楽で飯食ってる人ってすごいなと思った次第です。もっとも、その時のコバケンさんの指揮はねちっこくて、大げさで、正直あんま好きな第九じゃなかったです。
で、第九の話ですが、音楽の授業で先生が「第九をドイツっぽく演奏するのは違う」という話を聞いたことを思い出します。その先生によれば、第九の4楽章の旋律は教会音楽なのだそうです。確かに音が飛ばない、一音ずつ上がって下がるというのは教会音楽の一つの特徴ではありますが、言われてみればそうかも。だから、流れるように演奏するのがいいということで、その先生はスイス・ロマンド管弦楽団の第九を聴かせてくれました。
そして先日FMでゴンチチの番組を聴いていたらサイモン&ガーファンクルの「明日に架ける橋」をちゃんと聴きましょうという話題が出ており、番組の選曲を担当している音楽評論家の方が、これは教会音楽、讃美歌なんですよということで、白人のピアニストと、黒人のピアニスト双方のバージョンを比較して流してくれました。とても面白かったです。確かに明日に架ける橋も、教会音楽っぽいメロディーの作りで、白人のピアニストは讃美歌っぽく、黒人のピアニストはゴスペルっぽく弾いてました。あえてアート・ガーファンクル抜きのバージョン。これも悪くないです。
中世から続く教会音楽の影響がいまだにあるんだなと感心します。今晩はクリスマス・ソングではなくてあえて明日に架ける橋のいろんなバージョンを聴きながら仕事することにします。
聴いてるうちにベートーベンの第九を思い出しました。ブラームスの一番はベートーベンの第九に匹敵する交響曲をというような感じで作られたと言われてますが、メロディーが似てるところがあります。個人的には重厚で好きです。もしかして、テレビでのだめの再放送をやっていてどこかで刷り込まれたかもしれません。
私の中では年末だから第九、でも第九は聴き飽きたので似たやつ、でブラームスだったようです。もしかして、テレビでのだめの再放送をやっていてどこかで刷り込まれたかもしれません。
岡山にいた高校生の時、市民合唱に参加して一度だけ第九を歌ったことがあります。ドップラーフーガのとこの「ザーィントゥムシュルンゲン」って切り込んでくるテナーのパートが歌いたくてテナーで応募したのですが、声域が合わずベース行きを命じられました。全体練習でお目にかかった、近藤先生という合唱指揮者の先生がむっちゃ怖くてびびりました。合唱ってとてもストイック。合唱部とか無理だと思いました。でも、いざゲネプロの時に指揮者のコバケンさんが来て指揮したときに、合唱の練習でやったとおりにふったのでもっとビビりました。そういえば練習の時に、近藤先生が「ボクが指揮者と同じように振るから本人が来たら同じように歌ったらいいから」とか何とか言ってたのを思い出し、なんか音楽で飯食ってる人ってすごいなと思った次第です。もっとも、その時のコバケンさんの指揮はねちっこくて、大げさで、正直あんま好きな第九じゃなかったです。
で、第九の話ですが、音楽の授業で先生が「第九をドイツっぽく演奏するのは違う」という話を聞いたことを思い出します。その先生によれば、第九の4楽章の旋律は教会音楽なのだそうです。確かに音が飛ばない、一音ずつ上がって下がるというのは教会音楽の一つの特徴ではありますが、言われてみればそうかも。だから、流れるように演奏するのがいいということで、その先生はスイス・ロマンド管弦楽団の第九を聴かせてくれました。
そして先日FMでゴンチチの番組を聴いていたらサイモン&ガーファンクルの「明日に架ける橋」をちゃんと聴きましょうという話題が出ており、番組の選曲を担当している音楽評論家の方が、これは教会音楽、讃美歌なんですよということで、白人のピアニストと、黒人のピアニスト双方のバージョンを比較して流してくれました。とても面白かったです。確かに明日に架ける橋も、教会音楽っぽいメロディーの作りで、白人のピアニストは讃美歌っぽく、黒人のピアニストはゴスペルっぽく弾いてました。あえてアート・ガーファンクル抜きのバージョン。これも悪くないです。
中世から続く教会音楽の影響がいまだにあるんだなと感心します。今晩はクリスマス・ソングではなくてあえて明日に架ける橋のいろんなバージョンを聴きながら仕事することにします。
Posted by せさみん at 22:42│Comments(2)
│音楽
この記事へのコメント
はじめまして(^-^)
ブログはちょこちょこお邪魔してるんですが…。
第九に惹かれてやってきました♪
私は小学生の頃からChristmas前は第九の市民コンサートに行かされてて…いつか出たいと思いながら出れずじまい…。
第九を聞くと12月だなぁ〜って思います。
ブログはちょこちょこお邪魔してるんですが…。
第九に惹かれてやってきました♪
私は小学生の頃からChristmas前は第九の市民コンサートに行かされてて…いつか出たいと思いながら出れずじまい…。
第九を聞くと12月だなぁ〜って思います。
Posted by moco at 2009年12月24日 23:07
mocoさん
はじめまして。コメントありがとうございます。
第九、ぜひ一度参加されたら楽しいと思いますよ。
大分ではやってるのでしょうか。
はじめまして。コメントありがとうございます。
第九、ぜひ一度参加されたら楽しいと思いますよ。
大分ではやってるのでしょうか。
Posted by せさみん at 2009年12月25日 20:35